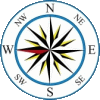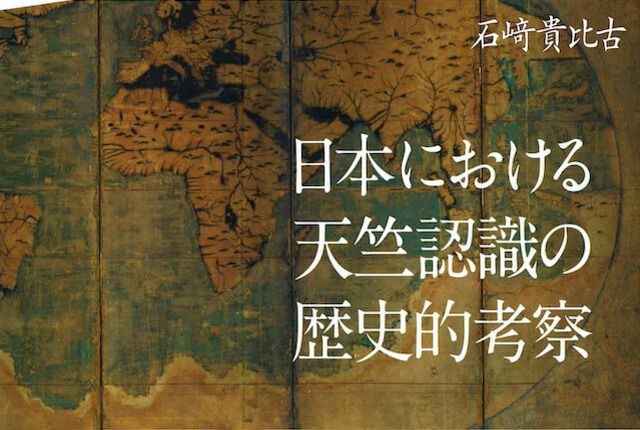2021年06月07日
天竺=インドではなかった? 日本人の天竺観の変化
天竺=インドではなかった? 研究者・石崎貴比古が明かす、日本人の天竺観の変化
6/6(日) 17:26配信
茨城県石岡市に鎮座する常陸國總社宮の禰宜も務めている石崎氏
天竺といえば『西遊記』で三蔵法師がお経を取りに向かう場所であり、天竺とはすなわちインドだ――というのが一般的な理解ではないかと思う。
当時の日本人の世界観が窺える「山本氏図」が描かれた同書のカバー
ところが日印関係史を専門とし、『日本における天竺認識の歴史的考察』(三元社)を著した石崎貴比古・東京外国語大学特別研究員/常陸國總社宮禰宜は、かつての日本人は「本朝(日本)・震旦(中国)・天竺」という三国で世界が成り立っていると認識しつつも、「天竺=インド」と考えていたわけではなかった(!)と言う。
また、ポルトガル領だったゴア経由で日本にやってきたイエズス会のフランシスコ・ザビエルらは「天竺人」と呼ばれ、キリスト教(カトリック)は当初日本では「天竺宗」という仏教の一派だと思われていたが、しかし、インド亜大陸から来たはずのザビエルたちは「日本人が言う『天竺』なる場所に行ってみたい」と思っていたという。天竺とはいったいどこだと思われていたのだろうか?
■Sindhuが漢字表記の「天竺」になり、日本で「幻想の国」になった
――日本に住む人たちはおおよそいつごろから「天竺」という概念を知っていたのでしょうか。
石崎:6世紀半ば頃の仏教伝来に伴ってだと考えられています。当時は「三国世界観」といって、まず「本朝」(日本)、それから隣にあって直接交流のあった巨大な外国「震旦」(中国)、そして震旦の向こうにある仏教が生まれた国だけれども日本では行ったことのある人がほぼまったくいないがゆえに想像が膨らんだ「天竺」の三要素で世界を理解しており、たとえば朝鮮半島にある国などは「ない」かのように捉えていました。
インダス川流域の地域を指す言葉Sindhuが、仏教の経典をサンスクリット語から中国語に翻訳した漢訳仏典において「印度」「天竺」「身毒」などと表記されたわけですが、日本ではなぜか「天竺」が中世以降、お坊さんだけでなく貴族や武士、近世には知識人にも好んで特に使われるものになりました。
中国では別にそういうニュアンスはなかったのに、日本においては「天竺」が「中国の向こうにあるよくわからない、理解しきれない彼方の国」という概念として成長していったのがおもしろいところです。
――「仏教の聖地」以上のイメージですか?
石崎:これは神仏習合にも関係していますが、神社で祀られている神様が「天竺からやってきた」という縁起譚、由緒がいくつも見られるんですね。神道だけで考えると「天竺から来た」は変に感じるかもしれませんが、たとえばそういう広がりも見られます。
■「天竺人」ザビエルは、天竺がインドだとは知らなかった
――石崎さんの著書の中では、カトリックを布教にやってきたイエズス会のザビエルたちが日本で当初「天竺人」と呼ばれ、また「デウス」を「大日」などと訳すなどの現地化戦略もあって「仏教の新しい一派」として受容されたにもかかわらず、インド(ゴア)経由でやってきたことに当時の人々が無関心だったという興味深い指摘があります。このあたりのねじれの背景は?
石崎:初期のイエズス会の宣教師たちが「南蛮人」と呼ばれる前に「天竺人」と呼ばれていたことは、日本史研究者には「前近代人の無知ゆえだろう」と思われていました。キリスト教がやってきたとき日本列島にはそういう宗教が存在しなかったがために、当時の人々はもともと自分たちが知っている仏教や神道の枠組みをあてはめて「神様がどうとか言っているから、坊さんか。じゃあ天竺のやつだ」と理解して「天竺人」と呼んだのだろう、と。彼らは見た目もアジア系ではなかったですから、震旦の向こうから来たに違いない、と考えたはずです。ただイエズス会士たちと話をしているうちに「どこから来た?」「インディアだ」と――もちろんおそらくポルトガル語で、ですが――「インディア? 知らないところだな。じゃあ、天竺人じゃないのか」と日本人たちは思った。逆にザビエルたちは「日本人が言っている『天竺』は中国のさらに西にある、仏が生まれた場所らしい。いったいどこだ?」と(笑)。具体的にこういう会話の記録が残っているわけではありませんが、史料を精査していくと日本人側もイエズス会士たちもお互いによくわかっていなかった状況が見えてきます。日本人はインディアがどこか知らなかったし、イエズス会士たちが仏教の由来や展開を理解するのはずっと後の話です。インド亜大陸にヨーロッパ勢力が進出する16世紀にはもう仏教は滅んだあとで、ムガル帝国はイスラーム、南インドはヒンドゥー教が支配的だった。日本に来るまでにイエズス会士たちが経由してきたシャムやビルマのあたりには仏教があったけれども、それが日本の仏教とルーツが同じ宗教だとはわからなかった。
――近世には東南アジア、シャム(タイ)が天竺と同一視される場合もあったそうですが、これも不思議です。17世紀に作られた地図「山本氏図」では、インド亜大陸には「なんばん」、タイ付近には「てんぢく」と書かれていたと。
石崎:これも歴史学者によって「近世人の無知による誤解」だと思われていた部分なのですが、そもそも日本人にとって天竺とインドはイコールではなかった。そして南蛮貿易をしていた時代には、現在で言う東南アジアに日本人町があって山田長政らが活躍していました。山田長政たちは「中国ではないさらに先の地域」に行っていたわけです。だからそこは「天竺」なんだ――と、こういう認識だと推察されます。ただ天竺が中国よりも南側にイメージされる場合と、西側にイメージされる場合の2つがあって、徐々に南アジア、西アジア、シルクロードに関する知識が整理されてくると、もともと天竺と呼んでいた場所はインド亜大陸の北のほうにあると日本人もわかってくる。それで一時期を過ぎるとシャムのあたりに天竺と書かれることはなくなっていきます。
■天竺認識の変化は、日本人の自己認識の劇的な変化を意味する
――近代に入って、天竺=インデアにヨーロッパ人が足を踏み入れ、あるいはその前からムガル帝国によって大部分が占領されていたという情報が日本に広まることによって、人々の世界認識はどう変わったと捉えればいいでしょうか。
石崎:江戸時代には一般の人にも歌舞伎や浄瑠璃、黄表紙の題材――つまり物語の舞台として「天竺」は親しまれていました。仏教のお坊さんたちもひとりも実際には行ったことはないのに「お釈迦様が天竺で云々」と物語を通じて誇大に語っていた。ですから仏教の祖国、聖地であり、不思議なものが生まれているファンタジックな国だと思われていたわけです。
それが江戸時代後期には蘭学の知識が蓄積されると、天竺とインドが近づいていきます。ムガル帝国が滅ぼされ、われわれがヨーロッパ人と呼ぶ人々にその土地が占領されてしまったのだと知ると、到達不可能だったはずの天竺がリアルな場所として立ち現れてきます。
「仏教系世界図」と呼ばれる近世の地図では世界のほとんどが天竺として描かれ、そのちょっと上に震旦があり、さらにそのはじっこに本朝があると思われていました。けれども近代になると現代のものに近い世界地図を一般の人も目にするようになり、三国世界観は完全に崩壊します。世界は三つでもないし、天竺は震旦より大きな国でもなかったのか、と。
――天動説が間違っていて地動説が正しいとわかった、くらいの衝撃かもしれないですね。
石崎:私は東京外国語大学出身なのですが、外語大に入るとほぼ必読になる文献がエドワード・サイードの『オリエンタリズム』とベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』です。ひとことでこの2冊が言うことを表せば「自国認識はイメージと関わっている」――つまり日本人が「日本」という国、「日本人」という自己認識を形成するにあたっては他者なしではありえない。「われわれ」と「彼ら」があるからこそ「われわれ」がどんな存在なのかを規定できる、ということです。近世までの日本に住む人たちは自画像を描く際に、現実に存在する巨大な隣国・震旦と、想像上の国・天竺を引き合いに自らを位置づけていた。それが近代にはガラガラと崩れた。
私たちは「よくわからないもの」に対峙したとき、どう振る舞うのか?
――震旦・天竺とではなく欧米列強や清と比較して自分たちを考えるようになった、と。そう考えると非常に大きな変化ですね。明治時代に浄土真宗の島地黙雷が岩倉使節団に同行してインドで釈尊の仏跡を訪れていますが、石崎さんの天竺認識史的にはこの行為はどう捉えられますか。
石崎:ついに仏教関係者が天竺に到達できるようになった、そして仏教を信奉する人たちは近代に入っても天竺に対する想いを失わなかった、と言えます。たとえそれが古代以来イメージしていたものとは違っていたとしても、かつてお釈迦様たちが瞑想し、修行し、教えを説いた場所として、仏教学的な意味合いにおいても「天竺」と「インド」が合致し、それを疑わなくなった時代が始まりました。
――なるほど。手の届かない「行けない聖地」から、具体的に存在する「行ける聖地」になったと。天竺認識の変遷を知ることで、今を生きる私たちにどんな示唆があると思いますか。
石崎:多くの科学者は「サイエンスがこの先いくら発達したとしても、人間にはまだわからない部分が残り続ける」と思っています。そのわからないもの、知らないものと対峙したときに、人類はどう振る舞うのか。今回の新型コロナウイルスによってもそのことが問われたわけですが、天竺は日本人にとっては長いあいだ想像上の聖地として捉えられてきたものです。天竺認識の歴史は、言ってみれば、われわれが「よく知らないけれどもありがたい」と思うものに対して何を期待して、どう振る舞い、その幻想がいかに霧散していったかという「未知に対する精神史」と捉えられます。世の中から未知のものがなくならない以上、似たような振る舞いはおそらく繰り返される。だからこそ現代の私たちも顧みる意味があるのかな、と思っています。
|
|